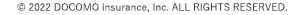|
小さなお子さんを育てながらも、自分の将来を考えているとはとてもいいことですね。夢を叶えるべく頑張ってください。
家計の現状を見ると、お父様と同居されていることもあって、毎年100万円程度を貯蓄する余裕があり、すでに1,000万円もの貯蓄もありますので、健全な状態といえるでしょう。次のステップ(夢の実現)に進む準備が整っています。
とはいえ、今後子どもが大きくなり、お父様が高齢になれば、生活環境や家計状況も変化していくと思われます。単にお金を貯めるだけでなく、変化に対応できるような心の準備も必要となります。
今後20年間のイベントとプランを書き出してみる
将来のことを考えるとき重要なのは、そのときの自分の年齢に加えて、関係する人々(伊藤さんの場合はお子様とお父様)の年齢やイベントも念頭に入れてプランニングしていくということです。図表2(別ウィンドウ表示)のような表を作って、今後20年間のイベントとプラン(予定)を書き出してみましょう。夢やイベントが具体的な目標になり、やるべきことや、問題点も見えてくるはずです。
伊藤さんご自身については、保育士資格の取得、保育士への転職、保育園開業という3段階の目標があります。現在は第一段階に向かって進んでいる途中です。一方、お子様については成長するとともに手がかからなくなる代わりに、小学校、中学校、高校と進学するにしたがって、衣食にかかる生活費や教育費の負担が大きくなってきます。また同居しているお父様も10年後には78歳。病気や介護の心配が現実的になる年齢になります。
お子様については、教育費の負担が特に重くなるのは中学校から大学(または専門学校など)までの8〜10年間です。公立に通っていても、塾や予備校に行けば数十万円単位のお金が必要になります(記入例は3または4年間にかかる費用の合計額)。大学以降の分として約500万円、余裕があるなら1,000万円準備しておけば、中学生以降の教育費の負担感が大幅に減ることになります。
お父様については、別途収入があって独立した家計運営が可能であり、また伊藤さんもお父様の収入に頼って生活しているわけではないので、その点は安心です。心配なのはお父様にもしものことがあったときに、今の住まいに住み続けられるか(引っ越すなら家賃支出が現在の3万5,000円より増える可能性)ということと、家が老朽化したときの修繕費は誰が負担するか(お父様に蓄えがなければ伊藤さんが払うことになるかもしれない、そのための資金準備が必要)ということです。住まいについてはお父様とも相談して、いざというときの対応策を考えておきましょう。病気や介護が必要な状態になったときには、周囲の助けや有料のサービスを上手に利用して乗り切る方法を考えましょう。
保育士への道
保育士の資格を取るには、資格が取れる大学や専門学校(通信過程を含む)に行く方法と、通信教育の教材などを使って自分で勉強し、国家試験を受ける方法があります。伊藤さんは後者を選択されているようですので、その前提でアドバイスします。
保育士の試験にはいくつかの科目があり、科目別合格の実績は3年間有効ということですので、試験を受け始めたら3年以内には何があっても全科目合格しないと、最初の年に合格した科目をやり直す必要があり無駄になります。ですから最初の試験から3年間は、試験日に照準を合わせた年間スケジュールを立てて、試験勉強に集中する必要があります。
伊藤さんはすでに通信教育での勉強を始められているようですので、今年あるいは来年からの3年間は試験最優先の生活ができるよう計画を立てましょう。
試験に合格して資格を取得したら、次のステップは保育園等への再就職です。採用にあたっては、経験者が優遇されるケースが多いことから就職は簡単ではないと思われます。また保育園の多くが民営化されつつあり、給与面での待遇はいいとはいえないのが現状です。保育士としては新人ですから、現在の年収手取り310万円より収入が減ることは覚悟しておく必要があります。なお、子どもが通う保育園に勤務するというのは、現実問題として難しいと思います。
家計が現状のままで、年100万円のペースで貯蓄できれば、5年後の貯蓄残高は1,400万円前後となり、教育資金や万一の備えは準備できるので、多少の収入減は受け入れられると思います。保育士の資格はとりあえず取っておいて、再就職についてはあせらずにそのときの家計の状態や、いい働き口がみつかるかなどを考えながら、決断されることをお勧めします。
保育園の開業
保育園の開業は大事業です。長期的な計画を立てて、しっかり準備してください。
保育園の開業・運営にあたっては、経営手腕、運営のノウハウ、子どもへの対応など、プロの業が求められます。自分ひとりで起業するのは難しい分野です。ひとりでやろうと思わず、保育士として働く間に考え方を同じくする仲間を増やしておきましょう。
働いて子育てをしながら起業するというのは大変ですが、たとえば、お子様が小学校に入学する頃保育士として働き始め、10年後に設立準備を開始し、その2年後に設立という目標を立てたとすると、設立時にはお子様は大学生です。心強い支援者となっているかもしれません。
保育園設立という大きな目標があれば、保育園勤務中もただ雇われて日々を過ごすのではなく、経営者としてどうすればいいか、という目線で仕事に取り組むことができます。そうすれば、自分のスキルも上がるし、いい仲間が集まってくると思います。
どんな資格でもそうですが、プロとして仕事をしていくなら、資格取得はスタートラインに立つためのパスポートに過ぎません。資格を取って実際にその仕事を始めてからどうやってその仕事に取り組むかが勝負です。
遺言書で子の後見人を指定しておきましょう
シングルマザーがやっておくべきことのひとつに、遺言を書いておくことがあります。シングルマザーの場合、子どもの親権者は自分ひとりなので、自分に万一のことがあった場合、お子さんのその後の生活を誰が見るかが問題となります。伊藤さんの場合、お子さんには18歳まで遺族年金が支払われますし、預貯金や生命保険などもあるので、金額的な面ではそれほど心配いらないでしょう。しかしそのお金を誰がどうやってお子様のために使ってあげるか決めておかないと、大金を残したばかりにお子様の養育をめぐり争いが起きるかもしれません。なお、元夫であるお子様の実夫が親権者となることもできますが、血がつながっているからといって、優先的に子の保護者となるわけではありません。
お子様の養育で争いが起きた場合には、裁判所で誰がふさわしいか決めますが、遺言書で後見人を指定しておけば、伊藤さんが望む人にお子様の生活を託すことができます。伊藤さんの場合、お父様はお子様が成人する頃には90歳近くなることを考えると、信頼できる別の人(ごきょうだいや親族、友人・知人など)に、いざというときの子の後見人をお願いするのがいいでしょう。遺言書に関しては、「自筆遺言」だと内容に不備があって無効になることもあるので、公証人役場で「公正証書遺言」を作成することをお勧めします。
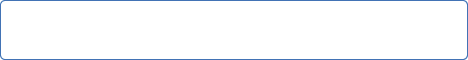
GE Moneyの住宅ローンがあります。知ってました?
|