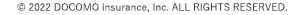| ■アドバイス |
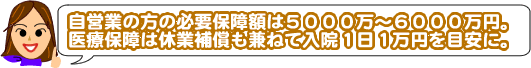 自営業の方は、会社員の方よりも社会保障が少なくなるため、生命保険などで準備することが、より大切になってきます。 まず、万一の場合の保障について考えてみましょう。 自営業の方に万一のことがあった場合には、遺族基礎年金が支払われます。しかし、これはどの家庭でも支払われるわけではなく、高校生以下(18歳になった最初の3月31日まで)のお子様がいる家庭だけになります。金額はお子様の人数によって次のようになります。 ● 遺族基礎年金の年金額(平成14年度)
お子様がいらっしゃる場合には年間104万円〜134万円が支給されますが、これではとても生活費には足りません。そして、お子様が高校を卒業したら、遺族年金は全くなくなります。 自営業の方で賃貸住まいの場合、死亡保障は5000万〜6000万円程度が目安です。また、事業のために借入をするならその分も保障を上乗せする必要があります。 現在、ご主人が加入されている年金型特別養老保険は、満期保険金が受け取れる貯蓄タイプの保険のため、大きな死亡保障を得るには向いていないといえます。このような場合は、割安な保険料で大きな死亡保障を確保できる「定期保険」で準備することをおすすめします。 ただ、ご主人は入院歴があるということなので、一定期間新しい保険に加入できない場合や、保険料が割増になる場合があります。現在ご加入の保険会社に、まず相談してみてください。 自営業の方は公的な医療保障として国民健康保険に加入しますが、会社を退職後20日以内に手続きをすれば、会社員のときと同じ健康保険を2年間継続して加入することができます(任意継続被保険者)。4月から健康保険の窓口での自己負担が3割になるため、国民健康保険と同じになりますが、毎月支払う保険料が異なります。 健康保険の月間保険料は税込み月収(標準報酬月額)の8.5%で、在職中は会社が半分負担しますが、退職後は全額自己負担になります。税込み月収30万円の場合、300,000×0.085=25,500、退職後の毎月の保険料は25,500円で、扶養家族が何人いても同じ保険料です。 一方、国民健康保険の年間保険料は前年の収入をもとに計算する所得割と、1人当たりいくらという被保険者均等割の合計となり、市区町村によっては世帯別平等割、資産割などもプラスされます。東京都の例では、住民税額(年額)×1.94+26,100円×被保険者数で計算され、住民税10万円、被保険者数3人の場合は (100,000×1.94+26,100×3)÷12=22,692、月々の保険料は22,690円です。 ただし、健康保険の保険料は4月よりボーナスも含めた総報酬制に変わること、国民健康保険の保険料は市区町村ごとに異なることから、退職前に会社と市区町村役場でそれぞれの保険料を試算してもらってください。また、国民健康保険には傷病手当金(4日以上休んだ場合に給料の6割が支給される)がありませんが、健康保険を継続した場合には引き続き保障される場合があります。その点についても社会保険事務所へ確認しておくといいでしょう。 ● 健康保険と国民健康保険の保険料
自営業の方は病気で休んだ場合、即収入減につながる恐れがあります。そのため、入院1日1万円程度の医療保障を確保しておくようにしましょう。また、所得補償保険もできれば加入しておきたいところです。医療保険では入院したときにしか給付金がもらえませんが、入院しないで自宅で療養することも考えられるからです。 まずは医療保険を優先し、事業が軌道に乗ってきたら保障の充実を検討してみましょう。 自営業の方の公的年金は国民年金のみとなり、毎月の保険料は1人13,300円、受け取る年金額は満額で804,200円(いずれも平成14年度)です。所得が少ない間は保険料免除の制度もあります。保険料を滞納すると老後の年金だけでなく遺族年金や障害年金も支払われなくなりますので、保険料が払えない場合はきちんと免除の申請をするようにしてください。 川村さんの場合、会社員だった期間の厚生年金も支払われますが、いずれにしろ公的年金だけでは十分な老後資金とはいえません。そのため、国民年金基金や個人年金保険で準備していくことが必要です。 国民年金基金は掛け金を社会保険料控除として所得から引くことができ、年金を受け取る時も公的年金等控除が使え、個人年金保険よりも税金面で有利です。 また、自営業者のための退職金制度として「小規模企業共済」も検討してみましょう。 川村さんは、事業が軌道に乗るまで家計も厳しくなると予想されます。お子様の教育費、老後資金の準備も必要になるので、いつまでに、いくら必要か、将来を見据えたライフプランを作ることが先決です。第一優先は、万一の場合の保障をきちんと確保することと、収入を増やすために努力することです。それから老後の年金、子どもの教育費などの準備を考えましょう。 学資保険については、「保険料を抑えるにはいつ加入するのがいい?」(1月)をご参考ください。 |
|