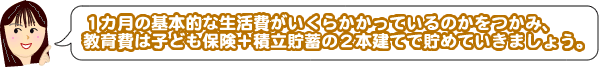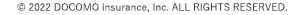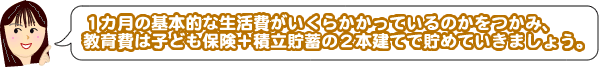
結婚1年目は季節ごとに冷暖房器具を買ったり、収納用品を買うなど、特別支出が多くなります。そうした分は別会計にして、基本的な生活費がいくらかかっているのか、データ収集していくことがまずは大切。結婚して1年(面倒だという人は数カ月だけでも)ぐらいは、できれば家計簿をつけると基本的な生活費を把握しやすいと思います。1カ月のおおよその生活費をつかんでからやりくりを考えていけば、赤字に悩む事なく、家計管理をスタートさせることができます。
現在は収納用品などの費用も毎月の支出の中に含まれているので家計は赤字ですが、別会計と考えれば収支トントンなので、やり繰りは今のままでOKでしょう。育児休業後は復職する予定とのことですが、将来は介護や育児などで美和さんが仕事を辞めざるを得ない状況になる可能性もあります。そうなった時に慌てないように、今からご主人の収入だけで毎月生活ができるようにしておくといいでしょう。ご主人の収入で基本的な生活費をまかなって、美和さんの収入からはレジャー費や貯蓄など、イザという時には削減可能な費用にあてるようにしていくと
ライフスタイルの変化に対応していきやすいかと思います。
教育費の準備方法についてですが、小林さんとしては「子どもの進学はオール公立(小・中・高・大学)で」というご希望です。でも思いどおりにいかないのが教育費の悩み………。特に高校以上は、お子さんの能力や運によっては私立を選ぶ可能性もでてくるかと思います。希望どおりにいかなかった場合に貯蓄を取り崩すことのないよう準備を考えましょう。「高校進学時に100万円、大学進学時に300万円」が一般的なケースの貯蓄金額の目標です。
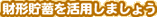
子ども保険で大学進学時の200万円はカバーできるので、残りの200万円分を積立貯蓄でまかなっていきましょう。
貯蓄商品としては一般財形貯蓄がイチオシです。非課税の特典はありませんが、利子補給や報奨金の制度がある会社も多いので、勤務先にお尋ねになってみては?また会社が「財形活用給付金制度」を導入していれば、育児・教育・介護などのために財形貯蓄を引き出した時に、
給付金を受け取ることができるので併せて問い合わせてみるといいでしょう。
万が一、進学時にお金が足りない場合でも、財形に加入しておけば雇用・能力開発機構から
最高450万円まで低利の融資が受けられるので有利です。美和さんが復職後、毎月4万円を積み立てていけば約8年(年利1%の複利運用の場合)で200万円貯めることができます。
育児休業中に節約してやりくりするコツをつかんで、復職後はバリバリとお子さんの教育費を貯めていっていただきたいと思います。
 ライフスタイルの変わり目に慌てない家計管理のコツ
ライフスタイルの変わり目に慌てない家計管理のコツ
 財形給付金・助成金制度
財形給付金・助成金制度