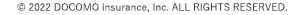| ■ご相談者 |
・貯蓄状況
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■アドバイス |
 中山さんの住宅購入プランを整理すると以下のようになります。
中山さんの場合、毎月の返済額(6万5369円)が今まで払っていた家賃(6万円)と同程度なのでムリなく住宅ローンを支払っていけるでしょう。5000円の負担増は今まで住宅財形に貯蓄していた分から回せばカバーできます。年間のボーナスの手取り額(124万円)から考えれば、ボーナス返済にも余裕があるはずです。 ただし購入後の家計のやり繰りは大変になりそうです。狭い賃貸から広い一戸建てに転居すれば、電気・ガス・水道代などの公共料金がアップします。また住宅購入後は固定資産税などの税負担が新たにかかってきますし、補修費の準備も必要でしょう。公共料金の負担増は毎月のやり繰りで、税金や補修費の準備は年間で予算をたててボーナスから確保して下さい。 今まで住宅の頭金として貯蓄していた3万円から住宅ローンの負担増分(5000円)を差し引いた2万5000円を教育費に回します。中学生になる長男の教育費の支出増に1万円、長男の進学費用の貯蓄に1万円、長女の進学費用の貯蓄に5000円と振り分けてはいかがでしょうか(商品については「教育資金作りは積み立てで」をご参照ください)。子ども保険で長男・長女それぞれに、高校進学時50万円、大学進学時に150万円用意できているので、ムリのないペースで貯めていけそうです。 中山さんは下のお子さんが小学生になったらパートに出る予定とのこと。老後資金の貯蓄はそれからでも遅くないのでは?住宅購入後は、まずローンの返済を軌道に乗せることを第一に考え、余裕があればミニ株や外貨預金などで老後資金運用の肩慣らしを始めてみてはいかがでしょうか。 パートを始めて収入が増えたら、(1)ローンの繰り上げ返済、(2)老後資金の貯蓄&運用、を並行しておこなっていきます。ご主人は現在41歳で、定年は60歳とのこと。25年ローンを利用すると、定年後にローンの返済がまだ6年も残っている計算になります。60歳前にローンを完済できるよう繰り上げ返済していく一方で、貯蓄&運用に励み、バランスよく老後の準備をしていってください。 住宅を買うときに自分の親や祖父母から援助を受けると、特例によって550万円までは贈与税がかかりません。ご主人がご両親から援助してもらう500万円は、通常ならば69万5000円贈与税がかかりますが、特例を利用すれば税金はゼロになります。特例を受けるためにはたとえ税額がゼロでも贈与を受けた翌年に申告しなければなりません。手続きを忘れずに行いましょう。 一方、知春さんが実家から受ける援助の300万についてですが、購入時の贈与でないと、この特例を利用することはできません。特例を利用できないと、贈与税が21万円かかってしまいます。また購入後に贈与を受けた300万円分(の土地or建物)については、知春さんの名義に変更することになり、新たな登記料もかかることになります。できればマイホームの購入を少し待って、知春さんの実家からの援助も頭金に入れる方がトクです。 財形融資の利用を検討しているとのことですが、利用前にメリット&デメリットの再確認を。財形融資は何といっても低金利(現在は1.27%)が魅力。財形貯蓄期間が1年以上で、残高が50万円以上あれば利用可能で、融資条件も緩やかです。反面、変動金利という点には注意が必要。5年間の固定金利なので、今後金利が上ると、5年後に返済額が大きくUPする可能性があります。利用するならローン返済の安定を優先し、知春さんの実家からの援助の分(300万円)、財形融資の利用額を減らすことをお勧めします。 また財形持家転貸融資は、勤務先のバックアップを受けて有利な借り入れができる反面、転職・退職時には原則として借り入れ金を一括返済しなければいけないというデメリットもあります。借りる前にもう一度よく検討してみましょう。 |
|