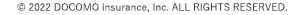| ■ご相談者 |
・ 収支の状況
・ 野村さんの悩み
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■アドバイス |
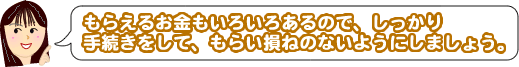 独身の時はお給料を全て自由に使っても誰にも文句は言われない生活ですが、結婚したら改めなければいけません。外食やレジャーは計画を立て、予算を組むようにします。おこづかいも2人合計で5万円ほどにおさめるよう話し合ってみてはいかがでしょうか。食費は外食費込みで月4万円に抑えることを目標に。これからは生まれてくる赤ちゃんのためにも、気持ちを引き締めて家計管理に取り組みましょう。 結婚当初は季節ごとに冷暖房器具を買ったり雑貨の出費がかさみがちですが、それらは別枠で考え、まずは食費・光熱費・通信費などの基礎生活費を固定させることが大切です。 また出産後、奥様や赤ちゃんの体調によっては奥様の仕事復帰が大幅に遅れることもあります。そうなった時に慌てないようにするためには、今からご主人の収入で基礎生活費をまかなえるようしておくことが大切です。ご主人の収入を基礎生活費にあて、奥さんの収入は収納用品の購入や貯蓄など、削減可能なものだけ出すように家計を組み替えていきましょう。 妊娠がわかると、出産までの数ヶ月は定期健診に通います。1回の検診にかかるお金は4,000〜6,000円程度ですが、血液検査などをする場合には1万円以上かかることもあります。ただし自治体によっては、一部の検査費用を負担する制度もあるので、お住まいの市区町村に確認することをお勧めします。検診の回数は出産までに13〜15回ほどが平均的ですが、個人の妊娠経過によっても変わります。通院時の検診費用や交通費は、確定申告時の医療控除の対象となるため、領収書は必ず保管しておきましょう。 出産の費用の平均は30〜40万円ほどですが、ホテルのようにゴージャスで至れり尽くせりのサービスに力を入れている産院では60〜70万円かかるという場合もあります。どうしてこんなにお金がかかってしかも病院によって費用にばらつきがあるかというと、正常な妊娠・出産には健康保険がきかないからです。出産は病気ではないため健康保険の適用外なのです。ただし妊娠中のトラブルや帝王切開などで医療処置を行った分に関しては健康保険が適用されます(差額ベッド代やTV代などの雑費は保険の対象外)。 平均的な産院での検診・出産費用は削ることができませんが、妊婦用衣料や、ベビー用品などのお金は夫婦(特に奥様)の考え方次第で、大きな差がでてきます。できればレンタルやリサイクル品などを上手に活用して、最小限の出費に抑えたいものですね。 妻または夫が健康保険に加入していれば子供1人につき30万円の出産育児一時金が支給されます。双子なら60万円もらえます。自治体や健保組合によっては上乗せとして、数万円の「付加給付」を支給している場合があります。例えば東京都23区では35万円となっています。出産にかかった医療費や扶養家族が増えたことを来年3月に確定申告すれば、税金が戻ってきます。 会社を休職して出産する人や辞めてから6ヶ月以内に出産する人は、出産手当金がもらえます。1日あたりの給与(平均額)の約6割を出産前後の98日分もらえます。また出産後育児休業を取っている間、雇用保険制度から平均給与の約3割が支給される「育児休業基本給付金」制度もあります。 こうした諸制度を使って、出産前後にかかる出費をカバーし「出産貧乏」を回避しましょう。 子供が生まれると、1人につき38万円を扶養控除として、所得から差し引くことができます。所得が高いほど税率が高いので、税金面だけで考えるなら「年収の高いほうの扶養とする」方が節税できます。でも忘れてはならないのが、会社によっては支給される「扶養手当」制度。子供1人につき毎月5,000〜1万円を支給する会社が一般的なようですが、制度のない企業もあります。最終的には「税金面+扶養手当」のトータルで得失を考えて、夫婦どちらの扶養とするか考えるといいでしょう。
|
|