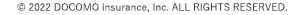|
日本の公的年金制度は、遺族保障については、配偶者(特に妻)と18歳までの子どもがいる家庭に手厚くなっています。逆に言えば、扶養されている親やきょうだいが遺族となった場合には、ほとんど保障がないのです。研二さんのケースはまさにそれにあたりますから、一般の家庭とは少し異なった考え方が必要になります。
遺族年金が受け取れるのは・・・
遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。
遺族基礎年金は、生計維持関係にある18歳未満の子を扶養する妻、または18歳未満の子が受け取れるものなので、子のない人の遺族には受給権がありません。
一方遺族厚生年金は、遺族基礎年金が受取れる人に加えて、子のない妻、55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)、18歳までの孫などが受け取れます。研二さんにもしもの事が有れば、お母様は受け取る事ができます。ただし、研二さんのお母様はすでに年金(遺族厚生年金)を受け取っているので、二重に遺族厚生年金を受け取ることはできません。現在もらっている遺族厚生年金と、研二さんが亡くなったことによる遺族厚生年金を比べて、どちらかを選ぶことになります。また、お姉様には、遺族年金の受給権はありません。
つまり、もし研二さんが亡くなった場合には、お母様の年金収入だけになってしまう可能性が高いということです。ただし、研二さんが勤める会社に退職金制度があったときには、お母様あるいはお姉様は死亡退職金が受け取れるはずです。
また、サラリーマンの配偶者の場合には、第3号被保険者(保険料を払わなくても第1号被保険者とほぼ同じ扱いとなる)になれますが、その他の扶養者は第1号被保険者として自分で保険料を払わなければなりません。
現在の家計状況と、対策(保険加入)
いただいた資料を見ると、お母様は無駄なく家計管理されているようで、月々の収支はプラス、ボーナスはほとんど貯蓄できる状態ですね。友田さんご一家の今後を考えると、400万円の貯蓄だけでは心もとないので、将来に備えて、ボーナス分(年間80万円)は貯めていきましょう。
現状のままなら、贅沢しなければ安定した生活を送ることはできますが、それは研二さんとお母様とお二人の収入があることが前提です。どちらかの収入がなくなると、どんなに節約してもぎりぎりの生活になります。
たとえば、万一お母様が亡くなると、年間192万円の年金分の収入が減り、食費や雑費を減らしてもボーナス分の余裕はなくなります(表1-1:お母様死亡後の家計)。
対策のひとつが、お母様が保険に加入できる健康状態であれば、お母様の死亡保障を準備しておくこと。67歳という年齢では、10年満期、保険金額500万円の定期保険で、月額保険料は約5,400円、10年間では約65万円の負担になります(通信販売の定期保険の場合の保険料)。とはいえ、当面の収入ダウンを補うための費用として、300万円〜500万円程度の保険に加入しておくと安心ではないでしょうか。
ただし、もしお母様がふつうの保険に入れない健康状態であるなら、無理して加入することはありません。健康状態にかかわらず入れる保険もありますが、それらは概して保険料が高く、少し長生きすると払う額よりもらう額の方が少なくなってしまうケースが多いからです。その場合、今より貯蓄ペースを増やして、万一に備える必要があります。
もうひとつの大きなリスクは、研二さんの死亡による収入減です。研二さんの年収はお母様の年金よりずっと多く、前述したように遺族年金によって収入減がカバーされることはありません。民間の生命保険で死亡保障を準備しておきましょう。
研二さんは年齢が若いので、10年満期、保険金額2,500万円の定期保険でも、月額保険料は約4,600円です(お母様と同じ保険会社で試算)。お母様の保険料と合計で月1万円の負担増ですが、これはいざというときに備える必要経費と考えて、加入しておくことをお勧めします。
「入院したときの経済的リスク」もありますが、それは多くても数十万円単位のことです。まずは金額面のリスクがより大きい「死亡したときの保障」について優先的に準備すべきと考えます。
| 新たに入る保険の例(保険料は、A保険会社で試算) |
| 研二さん |
: |
定期保険 死亡保険金額2,500万円 保険期間10年
月払い保険料 4,600円 |
| お母様 |
: |
定期保険 死亡保険金額 500万円 保険期間10年
月払い保険料 5,400円 |
お姉様の保険の見直し
本来死亡保障が必要な研二さんとお母様が保険に加入していない一方で、お姉様は合計で2,000万円もの終身保険に入っていて(表2-1:加入している保険について)、この保険料支払い(月額46,000円)は家計の大きな負担となっています。
終身保険には貯蓄性もあるので、お姉様の老後資金作りを兼ねて加入されたのかもしれませんが、現在優先すべきは、研二さんとお母様の死亡保障の確保です。病気のお姉様は新たに保険に加入することは難しく、また入院時の保障も利用する可能性が高いと思われるので、どちらか条件が有利なもの1本を残して解約してはいかがでしょうか?仮に《2》を残して《1》を解約すれば、保険料負担は月25,000円減ります。研二さんとお母様が新たに加入する保険の保険料(2人合わせた保険料は月額約10,000円)が増えても、差し引きで、15,000円の余裕ができます。余裕ができた分は貯蓄額を増やしましょう(表1-2:生命保険見直し後の家計)。( オススメの定期保険はこちら )
お姉様の国民年金について
お姉様の国民年金保険料が未納とのことですが、未納期間があると、万一障害者となったときに障害年金をもらえません。また保険料を納めた期間と免除期間を合わせて25年ないと、65歳以降に老齢年金をもらえないことになります。すぐに未納を解消しましょう。
ところで、「研二さん」と「お母様+お姉様」とは、世帯を分けて住民登録をすることを検討してはいかがでしょうか? 住所が同じでも別世帯として分けることはできます。各種の負担は世帯単位の収入で判定されることが多いので、世帯を分けた方が、社会保険料や医療費・介護費の自己負担など、さまざまな分野で負担が軽くなる場合があります。お姉様の年金保険料についても、一部免除が認められるかもしれません。
社会保険や税金の扶養の判定は、「生計維持関係にあるかどうか」であって「世帯が同じであるかどうか」とは別なので、世帯を分けて(世帯分離)いても、扶養家族とすることはできます。
細かな手続きなどは、詳しい専門家に相談されるといいでしょう。
|