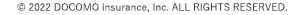|
|||
|
家計簿は、5年10年あるいはそれ以上先にある目的を達成するために有効なツールです。 ゴールを確認したらまず資金計画。今の貯蓄ペースで実現できるか、難しければやりくりできるかをチェックします。ゴールは一つとは限りません。今しなければならないことや、先のことでも大事なことなど、優先順位を考えながらアドバイスさせていただきます。 |
||
| ■ご相談者 |
| ■アドバイス |
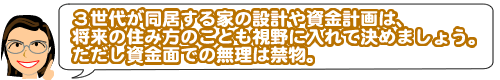 3人のお子さんがいらして、これだけ生活費を抑えた上、貯蓄ができているのはよく家計を管理されている証拠ですね。 ただ、ローンを抱えると貯蓄が難しくなるのも確か。無理な資金計画は禁物です。 具体的な設計はこれから、とのことですが、ご両親とどのようにお付き合いし住まわれるのか、それによってはキッチンを2つ作ったり介護しやすい構造にするなどの工夫が要りますし、当然費用も違ってきます。建替え費用だけでなく、同居後の光熱費など生活費の分担についても話し合っておくことは、資金計画を立てるだけでなく、お互い気持ちよく暮らしていくためにも必要な作業です。 ここに住宅ローンを借り入れた場合を考えてみましょう。 たとえば、建替え費用3000万円のうち2000万円を、返済期間20年、固定金利3%で住宅ローンを組んだとき、毎月の返済額は約11万円。これに固定資産税を加え、現在の家賃を差し引きすると月額にしてほぼ10万円の負担増加です。これではまったく貯蓄はできなくなってしまいますし、現在の貯蓄も、頭金や諸費用でほとんど取り崩さなければなりません。 学資保険の満期金は3人ともそれぞれ18歳で300万円程ですが、私立大学の入学金と4年間の学費だけでも平均400万円はかかりますので、年間100万円という現在の貯蓄ペースを大幅にダウンさせるのは避けたいところです。 支出は確実に増え、収入の見通しがあまり明るくはない現状では、たまき様の求職活動も給与重視となるでしょう。ただ必ずしも希望通りの職がみつかるとはかぎりませんし、単純に負担増をそっくりパート収入でまかなうというのでは、就労条件が変更になったときなど余裕がなくなることもあります。 可能であれば、ご両親に資金を贈与していただくか(注)、出していただいた資金額に応じて、建物を共有名義にする方法もいっしょに検討してはいかがでしょう。仮に費用の3分の1=1000万円を負担していただければ、現在の貯蓄を取り崩さずに済みます。また同居後に一定の生活費を家計に入れていただくことも相談してみては。 そうした援助が見込めない場合は、建築費を負担できる範囲に抑えるか、思いきって建替えを見送る判断も必要になるでしょう。 ご両親も老後の生活不安もおありでしょう。また、たまきさんご夫婦にも今後の生活設計があります。どちらか一方が我慢したり負担を背負うのではなく、事情をお話して折り合えるところを探してみましょう。
|
|