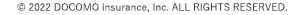|
|||
|
家計簿は、5年10年あるいはそれ以上先にある目的を達成するために有効なツールです。 ゴールを確認したらまず資金計画。今の貯蓄ペースで実現できるか、難しければやりくりできるかをチェックします。ゴールは一つとは限りません。今しなければならないことや、先のことでも大事なことなど、優先順位を考えながらアドバイスさせていただきます。 |
||
| ■ご相談者 |
| ■アドバイス |
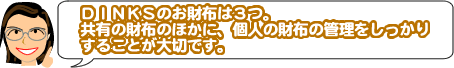 妻にもある程度収入のあるDINKSのご夫婦では、「共有の財布は最小限、あとはお互い干渉しない」ケースをよく見受けます。プライバシーを尊重するスタイルですが、反面、各自が自分の財布をしっかり管理していないと、どちらかが病気になったり、失業したり、あるいは家を買いたくなったときに、貯蓄がない、という事態が起きかねません。 川谷家はまさにこの状態。まとまった支出のなくなるこれからは、将来の備えや自己投資について、充分な計画を立てて実行していきましょう。 まず、共有の財布でカバーする生活費の範囲を決め、月いくらで生活するのか、車や電化製品の購入、旅行といった共通のまとまった支出の予定を、2人で確認します。 たとえば家賃は夫、光熱費は妻、というように分担する支出項目を決める方法もありますが、共有の口座は通常収入の多い方の名義で、公共料金の口座引き落としや自動積立定期などを設定しておきます。2人が生活費として使ったレシート等は月末に集計して、毎月の生活費を記録します。始めの2、3か月は生活費を把握するための調整期間と思ってのぞみましょう。 どちらかというと、収入の多い方の財布が緩みがち。自己管理が甘いときは、個人の財布を小さく、共有の財布をより大きくするのも一手です。 法律が整ってきたとはいえ、まだ派遣社員は正社員に比べて、収入や雇用が不安定です。健康保険の保険料など、どうしても必要な支出もあります。生活費の負担割合も、収入金額の比率そのままではなく、圭子様の負担を少なめに考え、収入の多いときは貯蓄に回すなどした方がよいでしょう。 病気など急な事態に備える貯蓄は、2人とも残高が把握できるように共有の財布(口座)の中で行います。共有の財布の中身は、生活費と共通目的の貯蓄です。 個人の財布でも、将来や自己投資に備えた貯蓄は必要です。収入がある以上、自分名義の貯蓄はしておきましょう。またスキルアップの費用や、仕事が途切れて収入が一時的にでもなくなったときのことは、考えておかなければなりません。収入がなくなっても生活費は取りあえず圭子様の貯蓄を取り崩すのか、それとも共有の財布の貯蓄から出すのか、ご主人の負担を増やすのか、話し合って、そのための備えはしておきます。 現在、仕送りがあっても生活が逼迫する状態ではないことから、3つの財布を合わせて、月10万円の貯蓄はできそうですね。 2か月以上の契約で、1か月の労働日数や労働時間が正社員の四分の三以上ある、などの条件を満たしていると、登録している派遣社員でも人材派遣会社の健康保険に入ることができますので、仕事の条件を確認してみてください。ただし、次の派遣まで空白があるとその期間は、国民健康保険への変更手続きが必要となります。その煩雑さを解消するため、派遣社員対象の人材派遣健康保険組合が今年5月に設立されました。派遣元がここに加入していれば、仕事の待機期間中でも任意継続という形で健康保険が継続できるメリットがあります。 会社の健康保険に加入した場合、厚生年金にも加入することになり、収入に応じた保険料(事業主と折半)負担が発生しますが、国民健康保険より保障が厚く、将来受け取る年金も増えるしくみです。 一方国民健康保険に加入するときは、同時に国民年金の保険料13300円/月(定額、平成14年度)の支払いも必要になります。国民健康保険の保険料は、市町村により前年の所得に応じて決まります。 現状で病気になると、医療費は全額自己負担になってしまいますので、いずれにしても早急に手続きを取って下さい。 |
|