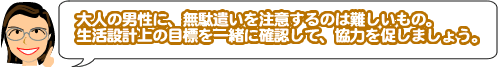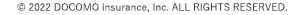| 平均的な月収(税金・社会保険料を除いた可処分所得) |
| 夫 |
170,000 円 |
| 妻 |
120,000 円 |
| 世帯合計 |
290,000 円 |
| 月間支出 |
| 家賃 |
57,000 円 |
| 水道光熱費 |
15,000 円 |
電話代
(インターネット代含む) |
8,400 円 |
NHK受信料・
衛星放送料金 |
7,300 円 |
| 食費 |
25,000 円 |
| 酒代 |
3,000 円 |
| ガソリン代(妻) |
5,000 円 |
| 日用雑貨・オムツ代 |
10,000 円 |
| 医療費 |
10,000 円 |
| 夫の小遣い |
30,000 円 |
交際費
(夫の両親との食事等) |
10,000 円 |
| リフォーム材料費 |
10,000 円 |
| 夫婦の生命保険料 |
24,400 円 |
| 自動車保険料(妻) |
8,200 円 |
| 学資保険 |
10,700 円 |
| 積立貯蓄 |
30,000 円 |
その他の貯蓄
(車検・夫の自動車
保険料分等) |
25,000 円 |
残金
(2等分して夫婦の
小遣いとする) |
1,000 円 |
|
|
 |
| ボーナス(年間) |
| 夫 |
579,000 円 |
| ボーナス支出(年間) |
| 夫の両親へ返済 |
100,000 円 |
| 生活費補填 |
150,000 円 |
| 夫婦の小遣い |
20,000 円 |
| リフォームのための貯蓄 |
272,000 円 |
| 貯蓄 |
37,000 円 |
| 貯蓄残高 |
| 預貯金 |
800,000 円 |
| 子どものための預貯金 |
360,000 円
(出産一時金等を貯めて) |
|
<<希望・予定>>
- 夫の実家の隣にある元おばあちゃんの家をリフォームして住む。
(現在、日曜大工でリフォーム中)
- 来年から子どもを保育園に入れたい。
<<住居>>
|