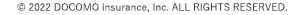|
|||
|
家計簿は、5年10年あるいはそれ以上先にある目的を達成するために有効なツールです。 ゴールを確認したらまず資金計画。今の貯蓄ペースで実現できるか、難しければやりくりできるかをチェックします。ゴールは一つとは限りません。今しなければならないことや、先のことでも大事なことなど、優先順位を考えながらアドバイスさせていただきます。 |
||
| ■ご相談者 |
・家計状況
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■アドバイス |
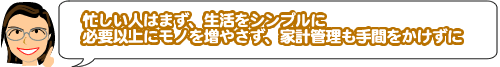 小さいお子さんがいてフルタイムで仕事をしている女性の場合、家事も引き受けることが多く、どうしても睡眠時間や自分のための時間にしわ寄せがきます。時間を確保するために、便利なサービスは利用しつつ、片付けや管理する手間が増えるのでモノは必要以上に増やさない、など生活のシンプル化を心掛けましょう。家計管理も生活スタイルにあった方法を選びます。 月10万円の減収はかなり生活ペースにも影響がでるはず。家賃など決まった額で減らせないもの、光熱費など減らせても限度があるもの、など減らしやすいものとそうでない項目がありますので、減らせる幅の大きそうなところから見直しましょう。 たとえば子供費は、平日はほとんど保育園と自宅の往復ですから、日常着は機能性重視、ご主人の趣味で着せたい服はお出かけ用に、と使い分ける方法もあります。おもちゃも、案外子どもはなくても遊べるものなので、これも工夫次第です。 ご主人にも、これまでとは違うということを家計簿などみせながら、理解をもとめましょう。小遣いをあればあるだけ使ってしまうなら、はじめに渡すのは昼食代程度にして、散髪代や交際費はそのつど請求するように変え、様子をみてはいかがでしょうか。夫婦の収入が同じくらいになるので、あまり差があるのも不自然です。 また、ボーナスが少ない分、年払の保険料などに備えて毎月積み立てているのはよいのですが、そのほかに不定期の支出が年間30万円余りあります。不意の冠婚葬祭など予定外のこともあるでしょうけれど、その枠をまず半分ぐらいにして、年間予算を立てた上、今すぐ必要でないものは衝動買いをしないように気をつけましょう。 共働きの場合、家計用の口座をもたない家庭もありますが、半田家は妻が一手に家計を管理しているタイプなので、夫婦個人と、家計用口座を基本に考えます。 家計用口座には、光熱費等の引き落としを集中させ、教育資金や車費などの積立は、予め一定額を自動的に定期預金に振り替えてくれる自動積立定期預金などを利用すれば、わざわざ預けかえる手間が省けます。 収入が同じなら、老後資金などは個人それぞれの口座で積立てましょう。 貯蓄といっても、年払保険料等その年のうちに支出に当てられるものを、特別費としてほかの口座に移していますが、家計用口座に残したままで構わないでしょう。口座を目的別に分けたり、現金を袋わけにして管理する方法は、感覚的にわかりやすい反面、細かく項目を分けすぎると、実際には月々変動のある家計の動きに対応できなくなったり、管理が煩雑すぎて続かないという弱点もあります。 年内に使う予定のお金や毎月の黒字分は引き落とし口座に残し、貯まったら定期預金等にすれば、振替の手間が少なくなるでしょう。浪費の傾向がある場合は別ですが、家計簿上でしっかり予算管理ができるなら大丈夫です。仕事をしているとなかなか銀行に行く時間も取れませんね。インターネットバンキングの利用を検討してみてもよいでしょう。 食費が多い、とくに外食を気にされていますが、その原因は時間がないことでしょう。まずは、内食と外食、外食も今日は疲れているから、というときと、誕生日などイベントのときと、項目を分けてみましょう。イベントではない外食は日常食。お惣菜を買ってきた方が安く済むなら、外にいく回数を減らして支出を抑えることができます。すべてを抑えるとストレスもたまるし長続きしません。イベントと日常を区別することで、抑えるところと出すべきところのメリハリをつけます。 もし食費が膨らんでいる原因が外食より、買い物の多さや割高なものを購入しているなら、買い物のし方そのものを検討する必要があります。 支出を減らすには、まずこれまでの支出そのものをじっくり見直し、なぜ出費が多いのか、原因を調べましょう。レシートなどで何をどう買ってきたか、無駄にしたものはないか、振りかえることも大切です。 もし時間がない、疲れている、ということが原因の大半であるなら、たまには家事には多少目をつぶって、休んでみましょう。 |
|