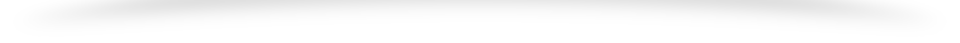目次
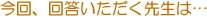
 井上 信一先生(いのうえ しんいち)
井上 信一先生(いのうえ しんいち)プロフィール |
|
 桜木範人さん(44歳 仮名)のご相談
桜木範人さん(44歳 仮名)のご相談
最近、周囲で病気や手術で入院する人が続きました。年齢的にも他人ごとではなく、大きな病に罹ったり手術を受けたりした際のお金の負担も心配に感じています。
入院した知人から、健康保険には高額医療費の負担が軽くなる制度があると聞きました。そのしくみについて教えてください。
|
桜木範人さん(仮名)の家族のプロフィール
|

高額療養費制度のしくみと注意点を踏まえ、対象となるケースを理解し手続き方法を確認しましょう
桜木さま、ご相談ありがとうございます。
ご相談にある制度とは、公的医療保険における『高額療養費制度』のことですね。健康保険に加入していれば医療機関に支払うのが本来の医療費の3割等の自己負担額で済むとはいえ、手術や治療費が高額になると負担も増してしまいます。そのために家計負担の軽減措置としてあるのが、『高額療養費制度』です。
高額療養費制度の対象となる医療費とは?
『高額療養費制度』を簡単に説明すると、医療費が高額になるような場合でも、年齢や収入(正確には所得)に応じて定められた「自己負担限度額」を超える分は負担する必要がないというものです。とはいえ、内容について色々と疑問も湧いてきますよね。制度のしくみは少し複雑になるので、クイズ形式で考えていきましょう。
Q1~Q2
(正解か不正解かを考えてみてください)
- Q1.入院した場合に医療機関から請求される全額が『高額療養費制度』の対象となる
- Q2.確定申告の『医療費控除』と同じく、『高額療養費制度』の対象医療費は1年単位で計算する
答え
『高額療養費制度』の対象となる医療費とは、健康保険や国民健康保険、後期高齢者医療制度等の「公的医療保険」の保険適用を受ける医療費(1割~3割等の自己負担割合が適用される保険診療)の、自己負担分となります。よって、入院や治療時に受ける保険外診療、例えば先進医療等は制度の対象外です。
また、入院時の「食事代」、「居住費代(テレビ等の病室の備品代や各種レンタル代等を含む)」、「差額ベッド代」等も制度の対象外です。入院した際に医療機関からは月ごとに入院費用等の請求を受けますが、その全額が『高額療養費制度』の対象となるわけではありません。外来時にはその都度、入院時は月ごとに、医療行為等を点数化した「レセプト」の形式で医療機関から診療明細書や請求書等を受け取りますが、この点数化された「レセプト」が、『高額療養費制度』の対象となる医療費と考えておいても差し支えないと思われます。
ちなみに外来時に薬を処方される場合、最寄りの調剤薬局等で薬を受け取りますが、処方された薬代も『高額療養費制度』の対象となります。
次に、『高額療養費制度』における対象医療費は、1か月間(カレンダー上の1日~末日まで)に医療機関から請求された金額(レセプト)ごとに計算します。例えば、外来や入院を問わず、月をまたいで生じた医療費は、同一の病気等のための治療費であっても合算できず、各月ごとに「自己負担限度額」を超えているのか否かを判断します。
確定申告の『医療費控除』とは異なり、『高額療養費制度』は年単位ではなく月単位で判断されることに注意が必要です。
よって、Q1もQ2も、残念ながら答えは「不正解」です。
「自己負担限度額」を超えているかどうか、合算できる場合、合算できない場合
保険診療に該当する自己負担分の医療費が、月単位で算出される「自己負担限度額」を超える場合に、『高額療養費制度』の対象となり、超過分の医療費が不要となるという概要は理解できたと思います。では、次の場合はどうでしょうか?クイズ形式で理解を深めていきましょう。
Q3~Q5
(桜木さん本人のケースで、正解か不正解かを考えてみてください)
- Q3.「自己負担限度額」を算出するための医療費は、一定額を超えたものだけが対象となる
- Q4.同じ病院で複数の診療科(眼科や内科など)を受診した場合や異なる病院で受診した場合でも「自己負担限度額」を算出するための合算をすることは可能である
- Q5.長男と長女の医療費も「自己負担限度額」を算出するための合算をすることは可能である
Q3~Q5の答え
結論として、Q3~Q5はすべて「正解」です。
『高額療養費制度』は、年齢や所得に応じて「自己負担限度額」が決まっていますが、このうち年齢については、70歳以上の方と70歳未満の方とで基準や計算方法も異なります。
まず、70歳以上の場合、1か月間の自己負担分の医療費の金額に関わらず合算して『高額療養費制度』を請求することができます。よって、単純に1か月間の自己負担の医療費が「自己負担限度額」を超えていれば、『高額療養費制度』の対象となります。
しかし、桜木さんのように70歳未満の場合、自己負担額が2万1,000円以上でないと合算対象に含めることができません。また、『高額療養費制度』の対象となる医療費は「レセプト」ごとに算出します。異なる病院で受診する場合は当然、「レセプト」も別々となりますが、同じ病院で受診する場合、現在「レセプト」は、医科・歯科と入院・外来の4区分に分かれています。逆に、総合病院等のように、内科や消化器科、循環器科、整形外科などの複数の診療科があっても、「レセプト」上ではすべて医科として括られます(歯科だけが例外)。
よって、70歳未満の方の場合、1か月間の医科、歯科、入院、外来の「レセプト」ごとに、自己負担額が2万1,000円以上ある場合、1か月間で受診した複数の病院について各「レセプト」の自己負担額が2万1,000円以上ある場合、各々では「自己負担限度額」に達していなくても、合算した額が「自己負担限度額」を超えていれば、『高額療養費制度』の対象となります。なお、外来で診療を受けた時に支払う医療費自己負担額と、その際に貰った院外処方せんをもとに調剤薬局で支払う薬代は合計でき、その合計額が2万1,000円以上あれば合算対象になります。
また、このほかにも『高額療養費制度』には2つの特例があります。
1つめは「世帯合算」。つまり、1人の方が1か月間にかかる医療費が僅かでも、家族の医療費自己負担額を合算して「自己負担限度額」を超えれば、『高額療養費制度』の対象となるものです。ただし、この場合の家族は、同じ「公的医療保険」の被保険者とその被扶養者であることが条件となります。
桜木さんの場合、ご本人である範人さんと、被扶養者であるお子さま(長男、長女)は、同居か別居かを問わず、同じ健康保険に加入していますので、同一月に各自の医療費自己負担額が2万1,000円以上であれば「世帯合算」の対象となります。しかし、共働きの奥さまは別の健康保険の被保険者、同居のお母さまは後期高齢者医療制度の被保険者と、加入している「公的医療保険」が異なっています。このようなケースでは「世帯合算」の対象とはなりません(同じ会社で働いていても各々が健康保険の被保険者である場合も合算の対象外)。
2つめの特例は「多数回該当」。過去12か月以内に3回以上、「自己負担限度額」に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、基準となる「自己負担限度額」が大幅に下がることになります。
具体的な数字で説明しますと、現行制度(2025年7月まで)において、70歳未満、年収約370万円~約770万円の方の場合の「自己負担限度額」は8万円強です。1か月間で1人の方の医療費自己負担額がこの額を超えるようなことは難しい場合でも、「レセプト」ごとに2万1,000円以上のものを合算、あるいは医療費自己負担額が2万1,000円以上となる対象家族分を合算することで「自己負担限度額」を超えれば、その超過分は『高額療養費制度』の対象となります。とはいえ、8万円強の医療費が続くのも中々の負担なので、直近12か月のうち4回目からは、「自己負担限度額」を8万円強から4万円強に引き下げてくれる制度となっています。
『高額療養費制度』の手続き方法
最後に、『高額療養費制度』の適用を受けるための手続き方法について解説いたします。
基本的に、この制度は事後申請により支払った医療費のうち、「自己負担限度額」を超える部分のお金の還付を受けるものです。しかし現在は事前申請、または「マイナ保険証」の利用により、基本的には窓口で支払う医療費を「自己負担限度額」内に抑えることも可能となっています。
まず、入院をする際には、一般的に必要書類中に、『高額療養費制度』に関する書類が含まれています。医療機関側から示される書類のうち、「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」等の書類を提出すれば、月ごとの請求金額を『高額療養費制度』に適応して自動的に精算してくれます。外来受診の場合で、医療費が高額と見込まれる場合にも同様の書類を提示されることもあります。
また、「マイナンバーカード」と連携された「マイナ保険証」で受診し、「限度額情報の表示」に同意すれば、入院・外来の区別なく、事前手続き不要で、高額療養費制度における限度額を超える支払分を精算できます。
とはいえ、とくに外来で同一月に複数の受診がある場合や家族の各々が受診する場合、本当は「自己負担限度額」を超えているのに請求漏れがないか不安になることもあるでしょう。このような場合、2年前まで遡って『高額療養費制度』の適用申請をすることは可能なので、疑問がある場合は「レセプト」や「領収書」をチェックしてみると良いでしょう。
※『高額療養費制度』においては、2025年8月、2026年8月、2027年8月と、3段階に分かれて改正が検討されています。本稿執筆時点(2025年1月)において、本稿にて記載した制度のしくみの概要部分については大きな変更の予定が発表されておりませんが、本稿ではあえて具体的な数字の記載を避けた「自己負担限度額」が、70歳以上の場合も、70歳未満の場合も、所得に応じてより細分化され、引上げられる方向となっています。
『患者申出療養』とはなんでしょうか。いわゆる『先進医療』とはどう違うのでしょうか。
病気での入院が短期化しているようですが、それでも医療保険に入っておくのが良いのでしょうか?
『マイナ保険証』に切り替えるためにはどのような手続きが必要ですか。またメリットはどのようなものか知りたいです。


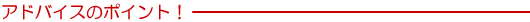

 桜木範人さん(44歳 仮名)のご相談
桜木範人さん(44歳 仮名)のご相談