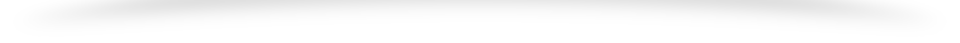目次
住宅購入を検討していたら、親が500万円を援助してくれることに。
親からの援助に贈与税ってかかるのでしょうか?
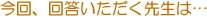
 鈴木 暁子先生
(すずき あきこ)
プロフィール
鈴木 暁子先生
(すずき あきこ)
プロフィール |
|
 金井健太郎さん(仮名 40歳 会社員)のご相談
金井健太郎さん(仮名 40歳 会社員)のご相談
一戸建てを買おうと話していたら、父親が500万円ほど援助してくれるという話になりました。援助はとてもありがたいのですが、贈与税を支払わねばならないのでしょうか?
|
ご相談者のプロフィール
|
|||||||||||||||

新築であれば贈与税はかかりませんが、
物件以外の諸経費の確認と無理の無い返済計画を。
物件以外の諸経費の確認と無理の無い返済計画を。
1.住宅取得資金の贈与には一定額の非課税制度があります。
金井さん、こんにちは。超低金利の今、マイホーム購入を検討する方が増えています。今回資金の一部としてお父様から援助を受けられるとのこと。ありがたいですよね。 贈与税のご心配をされていらっしゃるようですが、住宅資金の贈与については「住宅取得等資金の贈与税の特例」という一定額の非課税枠があります。
【「住宅取得等資金の贈与税の特例」の適用要件】
○贈与を受けた者が、贈与を受けた時点で日本国内に住所があること
○贈与を受ける者の父母や祖父母からの贈与であること
○贈与を受ける者が贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること
○贈与を受ける者の年間所得が2000万円以内であること
○贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住すること、または居住していない場合でも、
遅滞なく居住の用に供する見込みであること
これらの条件に該当すれば、この非課税制度を使えます。非課税枠は下表のとおりです。
1.現在(消費税が今後も8%のまま)
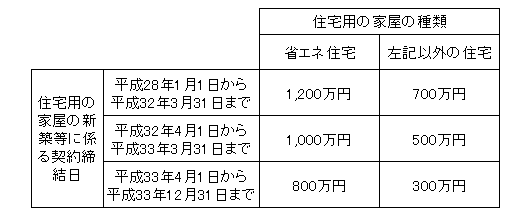
2.消費税が10%になった場合
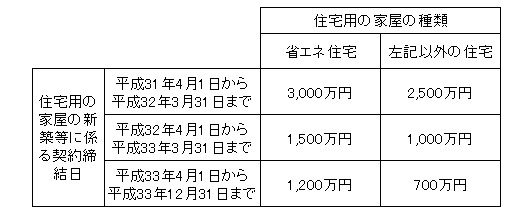
※国税庁 住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらまし
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf
なお贈与には、従来から「年間110万円までの贈与であれば非課税」という「暦年贈与」がありますが、この非課税枠も上記に上乗せすることができます。たとえば、平成29年に贈与を受ける場合、購入や新築した住宅が省エネ住宅であれば、1,200万円+110万円=1,310万円までが非課税枠となります。
2.確定申告が必要です
金井さんがお父様から500万円の贈与を受け、「住宅取得資金等の贈与税の特例」の適用を受ける場合、非課税範囲内なので結果的に贈与税はかかりませんが、この場合でも、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に確定申告が必要です。
確定申告時には
非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書
- 計算明細書
- 戸籍謄本
- 住民票の写し
- 登記事項証明書
- 新築や取得の契約書の写し
など、一定の書類を添付して納税地の所轄税務署に提出します。
また、マイナンバー制度の導入に伴い、個人番号を記載した申告書、申請書、届出書等を提出する場合は、個人番号カード等の本人確認書類のコピーも併せて添付する必要があります。
登記事項証明書の請求は、登記所の窓口や郵送での請求のほか、インターネットによるオンライン請求もできます。オンライン請求ですと手数料が安く、21時まで請求可能ですので便利かと思います。法務局のホームページを参考にされると良いでしょう。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html
3.住宅ローン減税の利用は注意が必要です
マイホーム購入後は住宅ローン控除を使われると思いますが、住宅取得資金等の贈与を受けた場合、借入額と贈与額の合計と購入額によっては注意が必要なケースがあります。
①借入額+贈与額が購入額以下のケース
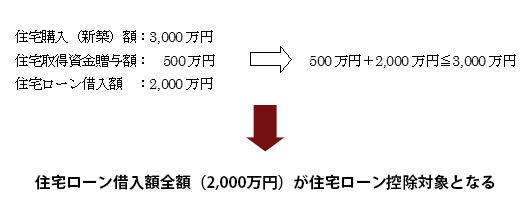
②借入額+贈与額が購入額を超えるケース
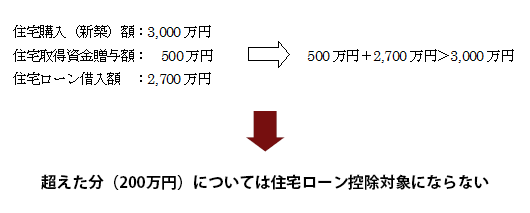
つまり実際の借入額は2,700万円であっても、住宅ローン控除の対象は2,500万円になってしまうのです。
住宅取得資金で贈与を受けた場合は、このように借入額と贈与額の合計と購入額の大小によって住宅ローン控除に影響があることに注意してください。
4.おわりに
住宅取得時には物件価格のほかに、登記費用や保険・税金などの諸費用は現金で用意しなければなりません。それに加え、引っ越し費用や新しい家具を購入するなどでそれなりの金額になってしまいます。だいたい、これら諸費用は住宅価格の5~10%ほどの出費と言われていますので、できれば頭金として総予算の2~3割程度は準備したいところです。ただし、現在の金井さんの貯金400万円をすべて住宅取得資金に回してしまうと、貯金がゼロになってしまいます。緊急予備資金として200万円ほどは現金を手元に残しておいた方が良いでしょう。
今回は、まだ物件などが決まっておられないので3,000万円と仮定しましたが、都内ですと物件価格はこれよりも上がってしまうかもしれません。それにより借入額を増やすことになると、贈与税の心配はなくとも、本来の資金プランに無理が生じるおそれもあり、元も子もありません。
よく、「借入れは年収の25%くらいまでが目安」と言われていますが、実際はもう少し細かい目線で確認したほうが良いでしょう。
たとえば、今後金井家はお子様の成長に伴い教育費の負担も大きくなり、40代から50代前半くらいがおそらく家計的にもっとも厳しい時期になると思われます。総額では目安の範囲内であっても、一時的に返済が困難になることも考えられますので、ローン契約を締結する前に、返済予定額で家計のシミュレーションをすることをお勧めします。
いずれにしても、もう少し自己資金を増やすなどして、まずは安全な資金プランを立てるようにしましょう。


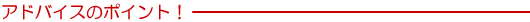

 金井健太郎さん(仮名 40歳 会社員)のご相談
金井健太郎さん(仮名 40歳 会社員)のご相談