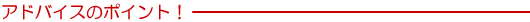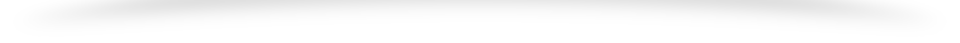目次
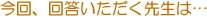
 鈴木 暁子先生(すずき あきこ)
プロフィール
鈴木 暁子先生(すずき あきこ)
プロフィール
|
|
 大友 浩一さん(仮名 59歳 会社員)のご相談
大友 浩一さん(仮名 59歳 会社員)のご相談
来年、60歳で定年退職となります。退職金をどのように受け取ればよいか迷っています。いくつか選択肢もあると聞いていますが、用語など違いがよくわかりません。
なお、現在の勤務先で65歳になるまでは継続雇用で働くつもりでいます。
|

定年後のライフプランとお金の使い道を考えて検討しましょう
1.勤務先の退職金制度を理解しておきましょう
大友さん、こんにちは。まもなく定年退職とのこと。お疲れ様でした。昨今は、継続雇用や再就職などでお元気なうちは働かれる方も多いですが、まずは一区切りといったところですね。退職を目前にした方からのご相談は、やはり退職金の受取り方が一番多いと感じています。また、その際に、勤務先の退職金制度をよくご存じない方も意外と多いようです。まずは勤務先の退職金制度を理解しておきましょう。
まず退職金の受取り方として「一時金形式」と「年金形式」があります。一時金形式は、その名のとおり原資を一括で受け取るものです。年金形式は、何年かに渡り、原資を分割払いしてもらうものです。受取期間には「終身」と「有期」の2種類があり、終身は亡くなるまで一生涯、有期は期間が限られているものです。一般的に有期は15年や20年などが多いように思います。また、「保証付」というのは、保証期間中に亡くなった場合でも、残りの原資は遺族に支払われる(=もらい損ねはない)というものです。
これらを踏まえて大友さんの勤務先の退職金制度をみてみましょう。
まず、退職金の原資は2つで構成されており、大友さんの場合は、第一年金が約625万円、第二年金が約1,875万円となるようです。
| 第一年金(25%) | 第二年金(75%) | |
|---|---|---|
| 原資 | 625万円 | 1,875万円 |
| 受取り方 | 一時金または20年保証付終身年金 | 一時金または20年保証付有期年金 |
| 備考 | 一時金と年金の割合を0~100%まで10%刻みで指定できる |
受取り形式や、受取期間などは企業によって異なりますが、これを見ると、大友さんの勤務先の選択肢は比較的柔軟だと思います。
2.一時金形式、年金形式のメリット・デメリットを理解しましょう
退職金の受取り方は、結局のところ、一時金形式と年金形式のどちらが良いかということに尽きるわけですが、それぞれメリット・デメリットがあるので、一概にどちらが良いとはいえません。このメリット・デメリットを理解していないと十分な検討もできません。それぞれの主なメリット・デメリットをみていきましょう。
| 一時金形式 | 年金形式 | |
|---|---|---|
| メリット |
・大きな所得控除がある ・使途自由な手元資金が増える |
・定期的な支給なので使うペースがわかりやすい ・公的年金の上乗せとして、生活費にゆとりができる |
| デメリット |
・1回のもらい切りなので、目的やプランがないと預金として寝かせるだけになる可能性がある ・使うペースに悩む ・まとまった金額が入ったことで、慣れない運用をして減らしてしまう可能性がある |
・給与や公的年金、その他収入などとの合計によっては社会保険料が高くなる可能性がある ・将来、介護サービスなどを受けるときの自己負担額が高くなる可能性がある |
一時金形式のメリットである「大きな所得控除」というのは「退職所得控除」というものですが、一時金形式を検討する上で重要なポイントになるので、これもしっかり理解してください。大友さんの退職一時金にかかる所得税は以下のステップで求めます。
① 退職所得控除を算出する
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円×勤続年数(※80万円に満たない場合は80万円) |
| 20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
※月数は切り上げ(例:37年4カ月⇒38年)
退職所得控除は勤続年数で決まりますが、大友さんは38年ですので、
800万円+70万円×(38年-20年)=2,060万円 となります。
② 退職所得を算出する
退職所得=(退職一時金の額-退職所得控除額)×1/2 で求めます。
大友さんの場合、(2,500万円-2,060万円)×1/2=220万円 となります。
③ 税率をかける
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円~329万9,000円まで | 10% | 97,500円 |
大友さんの場合、
220万円×10%-97,500円=122,500円
復興特別所得税=122,500円×2.1%=2,572円
となり、2,500万円の退職一時金をもらっても、約12万5,000円程度の所得税で済みます。
やはりこれは大きな魅力ですよね。
しかし、一時金はもらい切りですから、寿命がどれくらいかわからない中で、どのようなペースで使っていいのか悩ましいといった声も少なくありません。また、預貯金にしておくだけではほとんど増えません。とはいえ、運用経験者であればともかく、さほど運用経験のない人が、金融機関に言われるがまま金融商品を購入し、損失を被る可能性もあります。つまり使い勝手においては難しさがあるともいえます。
一方、年金形式の場合、定期的に支給されるので、生活費として使うペースがわかりやすいというメリットがあります。さらに受取期間が終身であれば、長生きリスクにも対応できます。しかし、年金形式の場合も一定の控除額があるとはいえ、退職所得控除のような大きなものではありません。また、年金ベースの生活といっても、公的年金や他の所得と合わせた金額が高めだと社会保険料が高くなる可能性があるのが、多くの人が嫌がるデメリットです。
3.目先の損得だけでなく、ライフプランに合った受取り方が重要です
いずれの受取り方でもメリット・デメリットはありますが、さらに重要なポイントとして、ライフプランに合った受取り方を検討しましょう。たとえば、住宅ローンの残債を一括返済したい、家のリフォームをしたい、適切な資産配分を考慮した資産運用の資金に充てたいなど、まとまった資金が必要なプランがあるなら、一時金形式で受け取る方が向いているかもしれません。逆に特にそのような予定はないというのであれば年金形式で受け取り、生活費にゆとりを持たせても良いかもしれません。
ただ、昨今、年金形式を終身で支給してくれるケースはあまり多くないと思います。その意味で、終身受取りができる第一年金は、個人的には年金形式を選択しても良いのではないかと考えます。また、第二年金も一時金形式と年金形式のミックスが可能ですので、住宅ローン残債分は一時金受取りをするという方法もアリだと思います。あとはセカンドライフでどのような生活をしたいのか、どのようなイベントがあるのかをご夫婦でよく話し合い、割合を検討していくとよいでしょう。その際は、ざっとした目安でよいので、キャッシュフロー表などを作成してみる、あるいはファイナンシャルプランナーに作成してもらうなどして、受取り方の違いを数値化してみると、よりわかりやすいと思いますよ。
老後の生活が心配です。必要な金額の確認方法や、自己資金の準備方法などアドバイスがほしいです。
定年退職後も元気なうちは働きたいと思っています。現在加入している確定拠出年金はどうなるのでしょうか。
老後資金を増やすため、定年後のオトクな働き方や年金の繰下げメリットを教えてください。