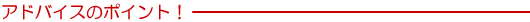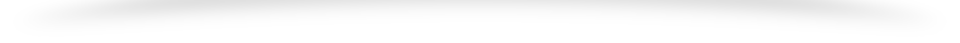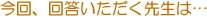
 髙柳 万里先生(たかやなぎ まり)
プロフィール
髙柳 万里先生(たかやなぎ まり)
プロフィール
|
|
 吉岡 彩さん(仮名)のご相談
吉岡 彩さん(仮名)のご相談
高齢の叔母の入院時の身元保証人になってほしいと依頼されています。入院が予定よりも長引くなど、想定外に高額となった場合の医療費等を、自分が負担することになるのかよく分からないため不安です。叔母の親族は現在自分以外にいないので、断るつもりはないのですが、身元保証人を引き受ける上で注意すべき点等ありましたらアドバイスを頂きたいです。
|
ご相談者プロフィール
|

負うべき責任の内容が不明のまま『身元保証人』を引き受けるのはお勧めできません。医療機関により責任の範囲が異なるため、事前に確認しておきましょう。
吉岡さん、この度はご相談ありがとうございます。叔母さまのご体調などご心配のことと存じます。また、『身元保証人』を引き受けるのが初めてとの事で、具体的なイメージが湧かないため、経済的な面でもご不安を感じていらっしゃるようですね。今回は、ご入院時の『身元保証人』を引き受けるにあたって、注意すべき点を解説します。
そもそも『身元保証』とは?
身元保証とは、ある者が他者に対して与えた損害について、身元保証人となった者が補填する契約や約束です。
身元保証には、次のようなものがあります。
雇用における身元保証
労働者が雇用主に損害を与えた場合、身元保証人が賠償金を支払う契約です。労働者に資力がない場合や音信不通になった場合でも、身元保証人に賠償金を求めることができます。
高齢者の身元保証
入院や介護施設への入所時に、支払いを一時的に立て替えたり、緊急時の連絡先になったりするものです。身元保証人は、契約内容に応じて費用の支払い保証、入院中・入所中のサポート、入院計画・ケアプラン・医療行為へのサポート、緊急時の対応、退院・退所時のサポート、死亡時の対応などを行います。
『身元保証人』とは
身元を保証する人を、一般に「身元保証人」といいます。高齢者本人が入院費などの費用を支払えなかった際に、「身元保証人」が肩代わりして支払うことを求められます。その為、身元保証契約を結ぶ際には、保証の範囲を明確に理解しておくことが重要です。
また、「身元引受人」という言葉もありますが、「身元引受人」は法的に使われる用語ではなく、その責任の範囲はケースバイケースです。身元引受人の場合、入院・入居していた高齢者本人が死亡した時に遺体を引き取ったり、残された本人の所有物を処分したりする役割を担うケースが多いようです。
『連帯保証人』との違い
『連帯保証人』とは、債務者が返済できなくなった場合に、債務者に代わって返済する義務を負う人のことです。債務者と同等の責任を負うため、債権者から請求されたら債務者と同様に全額を支払う必要があります。
| 名称 | 役割 | 責任の範囲 | 催告の抗弁権 | 検索の抗弁権 | 分別の利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連帯保証人 | 債務者と連帯して責任を負う | 100% | なし | なし | なし |
| 保証人 | 債務者が債務を履行しない場合に責任を負う | 限定的 | あり | あり | あり |
保証人に認められている権利には、次のようなものがあります。
催告の抗弁権
債権者から保証人に請求された場合、主債務者にまず請求してほしいと主張できる権利。
検索の抗弁権
主債務者に返済できるだけの財産があるにも関わらず、主債務者が返済を拒んだ場合、主債務者から返済してもらうか、主債務者の財産を差し押さえるように主張できる権利。
分別の利益
複数の保証人がいる場合、それぞれの保証人が借金全額の支払い義務を負うのではなく、保証人の人数で按分した金額だけを負担すること。
連帯保証人には、これらの権利が認められていないため、債権者は連帯保証人に対して債務者と同様に請求することができます。このように身元保証人と連帯保証人が負う責任の範囲は異なり、身元保証人が100%の損害賠償責任を負うことはありません。
医療機関が身元保証人を求める背景
2022年総務省公表の【高齢者の身元保証に関する調査】によると、病院や施設の9割以上が、入院・入所の希望者に身元保証人を求めています。また、身元保証人がいない場合『入院・入所をお断りする』と回答した病院・施設は15.1%にものぼることがわかりました。このように、多くの医療機関が身元保証人を求める背景には、単身世帯高齢者の増加により、医療機関等の負担が急増している実態があります。
医療機関等が困る主なケース
- ① 入院費や備品・日用品等の費用が回収できない
- ② 意思疎通がとれず、緊急時の連絡先がわからない
- ③ 本人の意思確認が困難なため医療行為の同意がとれない
上記のようなリスクを避けるため、
- ・医療費や諸費用の回収
- ・容体の急変時や死亡時等の緊急連絡先の取得
- ・意思確認が困難な場合の治療方針の判断
を目的として、入院時に身元保証人を明記した書類の提出を義務づける医療機関が増えています。
入院誓約書について
通常、入院時には入院誓約書という書類の提出を求められます。病院により入院誓約書の書式もさまざまですが、身元保証人または連帯保証人の記載欄が設けられていることが多いようです。
一般的な入院誓約書の記載内容としては、以下のようなものがあります。
- 1.入院料その他の諸費用については、入院者、連帯保証人又は身元保証人が指定の期日までに全額を支払います。
- 2.本人の身元については、身元保証人において一切引き受けをいたします。
- 3.退院を指示された場合は、指定の期日に身元保証人の責任において引き取ります。
- 4.貴院から指示された書類・証明書等は、指定の期日までに提出いたします。
筆者が2024年9月に都内病院にて入院した際は、入院誓約書の身元保証人・連帯保証人が負担する上限金額を50万円と設定するとの説明がありました。吉岡さんが心配されている医療費や諸費用の支払いについては、無制限ではなく上限金額を設けている場合がほとんどですので、書面に記載してある内容をよく確認しておきましょう。
想定される費用等を事前に確認
今回の叔母さまの医療費に関しては、高額療養費が適用されるため約7万円程度の予定とのことですので、医療費以外の費用についてもあわせて確認しておきましょう。病院により、パジャマやタオル、コップ等のアメニティセットをレンタルできる有料プランがあります。なお食事代やテレビ視聴カード代、個室を希望した場合の入院室料は全額実費となりますのでご注意ください。
【4週間(28日間)入院の場合の概算】
- ・医療費の自己負担金額が約7万円とする
- ・アメニティセットの料金が1日につき680円の場合
→28日×680円=19,040円 - ・食事一食につき490円×3=1,470円
→28日×1,470円=41,160円 - ・個室料金一日につき18,700円
→28日×18,700円=523,600円
合計653,800円となります。
もちろん、入院日数が長引く場合や検査等その他の医療費が別途発生する可能性はありますが、実際にかかる費用の概算や請求の流れ、退院時の支払方法につきましては、叔母さまに確認いただき、支払いの準備についても事前に共有されておくのが良いでしょう。
身元保証サービスの活用も検討しましょう
今回は、普段からよくコミュニケーションがとれている吉岡さんが叔母さまの入院時の身元保証人を引き受けるとの事ですが、将来的には緊急入院の際や介護施設への入所等、その都度叔母さまから依頼されたとしても、吉岡さんご自身が対応し続けるのが難しくなるケースも想定されます。そこで、『身元保証サービス』の活用についてもご提案・検討されてはいかがでしょうか。
『身元保証サービス』とは
身元保証サービスとは、身元保証人を代行する団体によって提供されるサービスです。
身元保証サービスは主に一般社団法人やNPO法人、株式会社が運営元となっていますが、サービス内容や料金は事業者により大きく異なります。
契約内容により所定の料金はかかりますが、身元保証サービスを利用することにより、吉岡さんご自身の負担が軽減され、叔母さまや病院にとっても緊急時に身元保証人に連絡がつかないリスク等を避けられます。最近では、病院と提携している身元保証サービス事業者も年々増えており、社会的なニーズの高さがうかがえます。何より信頼できる事業者を見きわめる事が大切ですので、吉岡さんや叔母さまだけで悩まずに、病院や管轄の地域包括支援センターに相談してみるのもお勧めです。
2025年現在、日本の人口の約5人に1人(18%)が75歳以上となり、少子高齢化に伴う高齢者人口の割合は増加する一方です。『おひとりさま』の高齢者の入院や介護施設への入所の際に欠かせない『身元保証人』のなり手不足は、深刻な社会的課題と言えるでしょう。
誰しもいつかは『おひとりさま』となる可能性がゼロではありません。身元保証人を引き受ける側も依頼する側も、日頃から万一の場合の身元保証をどうするかについて考えておく必要がありそうですね。
病気での入院が短期化しているようですが、それでも医療保険に入っておくのが良いのでしょうか?
一人暮らしの母を扶養に入れた方がいいですか?
今は元気な親。でも将来介護が必要になったらどれくらい費用がかかるのか心配です。