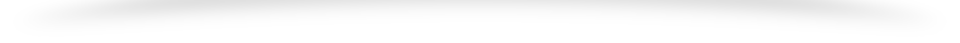目次
含み損を抱えている投資商品があります。
どのように対処すればよいでしょうか?
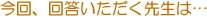
 井上 信一先生
(いのうえ しんいち)
プロフィール
井上 信一先生
(いのうえ しんいち)
プロフィール |
|
 斉藤 義一さん(仮名 41歳 会社員)のご相談
斉藤 義一さん(仮名 41歳 会社員)のご相談
2年半ほど前に金融機関から購入した投資信託が3割強値下がりしています。分配金は毎月入ってきますが、現状では元本に対して含み損が大きくなっており、このまま持つべきか、換金すべきかで迷っています。また、別の投資信託に乗り換えることも勧められていますが、いまは投資より住宅ローンの繰り上げ返済を優先するのが良いとの記事を読んで、ますます方向が定まらないでいます。
|
斉藤 義一さん(仮名 41歳 会社員)のプロフィール
|

投資もライフプランの実現のために行うのが理想です。
目的を設定して再スタートしましょう。
目的を設定して再スタートしましょう。
運用成果がおもわしくなく、気持ちも晴々とされていないことと察します。厳しい現実を述べると、投資金額が3割下がった場合、ここからさらに5割弱上昇しても、ようやく元の投資元本に戻る計算です。これを実現させ得る戦略を考えることも重要ですが、投資においては不確実な予測の域を超えられないゆえ、有効な方法を申し上げることはできません。しかし、将来の使途目的等を踏まえて現在の資産額を顧みることは、ライフプラン上では非常に大切です。斉藤家の場合で、ここから想定される将来図を考えてみたいと思います。
運用環境に対する期待と留意点を観察してみましょう
まずは、斉藤家の資産の大部分を託しており、まさに悩みの元にもなっている投資商品の実態とその運用環境の検証を考えてみます。お聞きした商品名から判断するに、投資されているのは、主にエマージング(新興諸国)の国債等に投資を行い、そこから得られる利息収入や為替差益、投資資産の値上がり益を目的とする投資信託と思われます(ただし、分類上は追加型株式投資信託に該当します)。また、複数の選択肢の中から適用通貨を選べる、「通貨選択型」であり、投資時期からの値下がり率等を勘案すると、おそらくは高金利通貨であるブラジルレアル等を選択されているのではないでしょうか。
一般的な外貨建て投資信託は、円貨で投資した後は決められた所定の通貨に替えられて運用されます。しかし、「通貨選択型」は任意で適用通貨を選べるのが特徴です。とはいえ、実際には個々の資金を様々な通貨に振り替えるわけではなく、ファンドが運用する資金自体は所定の通貨(一般的には米ドル等)に換金されており、これに高度な為替ヘッジ等のデリバティブ取引を付加する仕組みとなります。例えば、ブラジルレアル建てを選択する場合、ファンド自体の運用に加え、別途、米ドル売り・レアル買いの金融取引をオプションで行っていることになるわけです。また、米国よりブラジルの金利が高ければ、その金利差相当分も収益として見込まれるため、実に多角的な収益源泉を持つ投資信託として人気があります。
一方、仕組みが大変複雑であるため、どのような環境であれば運用効果を望めるのか、その判断も非常に難しくなるといえます。
債券の価格は一般的に景気拡大局面では下落方向に向かいやすくなります。これは、景気拡大に伴い金利も上昇している(またはその期待がある)ことが多いため、それ以前に設定された固定金利の債券の魅力が相対的に薄れるからです。この局面で上昇方向に向かいやすい株式等とは対照的な動きといえるでしょう。したがって、ファンド資金がどのような景気サイクルにある国々の債券に投資しているのかを注視する必要があります。経済の成長が著しい国の場合、たとえ高金利であっても債券自体の価格が思わしくない場合もあるからです。逆に、景気後退(金利低下)局面では、債券の価格も上昇方向に向かいやすくなりますが、この場合はその国の通貨安にも繋がり為替差損を被る場合もありますので、話はそう簡単ではありません。通貨選択型投資信託等の場合、投資を行っている債券国の通貨安による影響は軽減されますが、選択した通貨国の事情をチェックする必要があります。
このように、この投資信託は運用成果に与える要因が複雑に絡み合っています。選択した通貨と対円・対米ドルとの為替、通貨国と米国等との金利差、さらに、その通貨国の経済情勢だけでなくファンドが投資した債券の国々の事情にも注意を払わねばなりません。投資した国々の景気サイクル等により直接的な債券の運用成果が変動するだけでなく、万一、投資国の信用度が揺らぐとたちまちに債券価格が暴落することもあり得るからです。
また、通貨選択型として選べる高金利通貨は、概して資源国通貨であり、リスク性の高い通貨であることも多いため、世界的な経済・景気要因による影響も受けやすくなります。今般、深刻な問題となった欧州信用不安により、高金利通貨への投資が一斉に引きあげられ、この結果通貨安に動いたことは記憶に新しいですね。斉藤さんの運用環境の悪化に影響したのも、対世界各国に対する円高での為替差損によるところが大きいと思われます。この状況を観察したうえで、次にとるべき投資スタンスを検討されると良いと思われます。
家計環境の将来的な推移を考えましょう
次に、斉藤家の今後の家計環境について考えたいと思います。運用環境や運用商品だけを捉えた場合、もう少し様子をみて保有するスタンスを選択できたとしても、その成果が表れるよりもずっと前に、家計状況から資産を換金する必要性が高いことも考えられるためです。
さて、斉藤さんは、現状の家計の支出内訳を把握していないとのことですので、今回は額面年収から手取年収(可処分所得)の概算を算出し、そこから年間貯蓄額(年間収支)を差し引くことで、おおよその年間支出を把握する手段を試みます。
斉藤さんの場合、現在の額面収入600万円に対し、平均的な社会保険料率をもとに算出した各種社会保険料負担額、および住宅ローン控除額等を考慮した所得税・住民税を差し引くと、概算での手取年収は約500万円と考えられます。ここから年間貯蓄額である60万円を引くと、約440万円が年間支出となります。このうち住宅ローンの返済額135万円を除くと、日常的な生活支出は約305万円、月平均で25.4万円と見込まれます。額面年収に対し、貯蓄割合10%、住宅ローンの返済負担割合22.5%、その他支出割合50.8%ですので、お子様がまだ小さいことを踏まえると、やや支出割合が多めの印象も受けますが、緊急の改善が必要というわけではなさそうです。
さらに、お子様の成長に伴い増大が予想される支出を踏まえて概算で試算した家計推移が図表1です。
表1 斉藤家の今後の家計予測の概算
(万円)
| 現在 | 3年後 | 9年後 | 12年後 | 15年後 | 19年後 | ||
| 年齢 | 夫 | 41歳 | 44歳 | 50歳 | 53歳 | 56歳 | 60歳 |
| 妻 | 39歳 | 42歳 | 48歳 | 51歳 | 54歳 | 58歳 | |
| 子 | 4歳 | 7歳 | 13歳 | 16歳 | 19歳 | 23歳 | |
| 額面年収 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 手取年収 | 498 | 478 | 465 | 472 | 475 | 465 | |
| 年間支出 | 438 | 438 | 506 | 518 | 602 | 394 | |
| 年間貯蓄(収支) | 60 | 40 | -41 | -46 | -126 | 71 | |
| 金融資産残高 | 700 | 860 | 1,020 | 893 | 674 | 366 | |
| (内訳) | 預貯金 | 100 | 260 | 420 | 293 | 74 | -234 |
| 投資信託 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 住宅ローン残高 | 2,775 | 2,448 | 1,764 | 1,410 | 1,038 | 529 | |
※額面年収は、低めの試算を見積もるため、今後も変動しないものとして仮定
※手取年収は所得税・住民税算出のための各種所得控除やローン控除額を考慮し、推移額が異なる
※年間支出は、主に子の成長に伴う日常支出や教育費の増減を考慮
※金融資産残高に運用率は考慮しないが、各期間の年間貯蓄額(収支)が同様に推移すると仮定して算出
※住宅ローン残高は入手した情報をもとに算出した金額
この推移表から、お子様が中学に入学すると収支はマイナスに転じ、大学卒業までその状態が継続する可能性の高いことが読み取れます。そして、金融資産残高もしばらくは増え続けますが、大学入学時期には現在の水準以下(約670万円)までに戻り、老後を迎える頃には約366万円に目減りしてしまいます。
ここで、注目すべきポイントが3点ほど考えられます。
1点目は、試算結果の金融資産残高の推移に対し、投資資金を600万円と固定した場合、換金性のある預貯金等はおよそ15年後には底をついてしまうこと。このことは、現在投資信託に投入している投資期間の最長限度が15年以下であることを裏付けています。
2点目は、変動金利型である住宅ローンの適用金利がこの間に上昇に転じた場合、返済額の増加(年間収支の悪化)から家計の余裕度は低下すること。すなわち、金融資産残高の推移予測が成り立たなくなるため、返済額軽減型の繰り上げ返済により、年間収支悪化の対策を図る必要があります。つまり、換金性の高い預貯金の必要度が増すので投資信託に投入した資金の運用期間はさらに短縮化される可能性があることになります。
3点目は、今回の予測にはその他の一時的支出が反映されていないことです。家族のイベントとしての旅行や車の買い替えに資金を要す場合、先の前提はさらに悪化します。
以上から、当面は投資資金を動かす(換金する)必要性は低いものの、投資環境の好転時期を伺うよりもずっと前に資金需要が発生してしまう可能性もあります。万一、そのタイミングが今より深刻な運用状況であった場合、いくつかのライフイベントの制約を受け入れるか、強制的な投資資金のロスカットを余儀なくすることを覚悟しなければなりません。
税制の優遇策も活用して許容範囲額の換金も検討しましょう
上述した懸念がある以上、事前に防衛策を講じておくことも検討したいところです。そこで、計画的な換金(損失計上)をおこなって余裕資金の枠を高めてはいかがでしょうか。
とはいえ、いきなり全額を一度に換金する必要はなく、許容範囲額を少しずつ行えばよいと思われます。この際に活用したいのが、「上場株式等の譲渡所得における内部通算」と「上場株式等の譲渡損の繰り越し控除」となります。なお、この制度は、上場株式だけでなく公募追加型株式投資信託にも適用されるため、斉藤さんが投資している商品でも活用できます。
まず、「内部通算」とは、換金して確定した譲渡損益は他の上場株式等だけでなく、申告分離課税選択した上場株式等の配当所得と相殺できる制度です。現在、斉藤さんが保有している投資信託には、幸い定期的な収益分配金が支払われています。投資信託の分配金の中には投資元本の払い戻し(課税上は非課税)が含まれている場合もありますので、実際には分配金のうちこれを除いた金額だけが相殺の対象となります。ですが、配当額が比較的高いため、その相殺効果もある程度期待できます。現在、譲渡所得と配当所得の税率は同じですので、何もしなければ課税されている配当金相当額と換金に伴う手数料を考慮した分だけ、投資信託を換金し、損益を相殺させることで税金を浮かすことができます。
次に、「譲渡損の繰り越し控除」は、換金した年に生じた損失を、翌年以降3年に渡り、上場株式等の換金で得た利益と相殺できる制度です。万一、翌年以降に運用環境が好転し利益が生じた時や、別の投資商品で利益がでても、繰り越した損失と相殺できるので、やはり課税は生じません。
いずれの場合においても、確定申告をする手間はかかります。また、結果的には目論み通りにはいかない可能性もあります。少額ずつ換金していく手間もあるでしょう。しかし、購入時だけでなく換金時期を分散していく手法も分散投資としては有用性の高い方法です。仮に、換金後に運用環境が好転した場合でも機会損失を軽減でき、少額ずつでも預貯金等への資金移転を行なえますので、これを使う目的に合わせて活用する手立てが増すことになります。
投資を行う目的の再設定を検討しましょう
最後に、そもそも一番大切なこととして、斉藤さんにはこれを機に投資目的の再設定を検討頂きたいと思います。
投資を行う目的として、それは何にお金を使うためなのか、それはいつ、いくらくらい必要なものなのか、これらを決めておくことで投資金額や投資期間だけでなく、取れるリスクの高さ(目標とする金額に対してプラスマイナスでいくらまでの幅を許容できるのか)が明確になります。そもそも、株式が良いのか債券なのか、換金時期に制約があるのか否かなど、選ぶのに都合の良い投資資産も、このような目的によって異なるものです。
その際に考慮したいのが、使う目的の性格といえるでしょう。例えば教育資金のように必要な金額として可変性の低い目的のためには、将来の投資成果を定めることのできない投資資産は必ずしも相性が良いとはいえません。反対に、可変性の高い目的であれば、程度の差はあれ、投資成果に応じて適宜変更できます。例えば、数年先の旅行資金や自動車購入資金などが考えられます。投資の成果として上手くいけば予定よりグレードの高いもの、逆であればグレードを下げればよいと、割り切れるようなものから始めてはいかがでしょう。
一方、現状では準備不足気味な老後資金目的については、可変性はあるものの、そもそも将来の生活資金のためのものなので、あまりにも偶然の投資成果だけに頼ることには注意が必要です。適宜、柔軟に見直しのできる工夫を取り入れるのがよいでしょう。
以上を踏まえ、その一例をご提案いたします。
- 現在の投資信託については、いつ突発的に生じるか懸念される資金需要に備えて、少額ずつ換金することを検討する。
- 換金した資金と毎年の積立額を活用して、以下の目的に応じた資金への配分を毎年検討する(少額ずつ、毎年投資を行う〔購入時期の分散〕)。
- 繰り上げ返済資金用として一部を預貯金に割り当てる
- 自動車や旅行等の目的として一部を数年単位の積立型投資商品や預貯金等に毎年少しずつ割り当てる
- 老後資金を目的として、一部を長期的な投資商品に毎年少しずつ割り当てる。
なお、Cの老後資金目的用としては、20年程度を運用(保有)期間として据えるのも良いですが、期間が長くなるほど投資成果の予測も困難になります。そこで、5~10年程度等の短中期ごとに換金して再投資する方法を検討してもよいでしょう。なお、毎年投資する金額は少額ですが、これを一定期間継続することで、老後の換金時期を分散させることもできます。見方を変えれば、自分で準備する私的年金にもなるわけです。
投資を、運用商品や運用環境の面だけで捉えると、その換金に悩んでしまうことは多いと思われます。しかし、すべての資金は使う目的のためにあるわけです。ライフプランを前提にしてこれを捉えると、精神的に納得のいく場合も多いでしょう。また、そのための次なる打ち手を検討できる一歩に繋がると思われます。


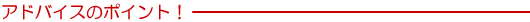

 斉藤 義一さん(仮名 41歳 会社員)のご相談
斉藤 義一さん(仮名 41歳 会社員)のご相談