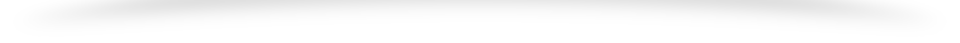親と子、祖父母と孫など、家族間でお金やモノをあげたり、もらったりということはよくあることです。普段はあまり意識しないと思いますが、やりとりするお金やモノが一定額以上になれば、贈与として「贈与税」がかかってくる場合があります。今回は、贈与税の仕組みや注意点を確認してみましょう。
贈与税の仕組みと計算について
贈与税は、個人からある一定額以上の財産をもらったときにかかる税金で、贈与税を払うことになるのはもらった人(受贈者)です。お金はもちろん、不動産や自動車などのモノも換算された金額に対して課税され、また、自分が保険料を負担していない保険金を受け取った場合や、宝石や絵画などの高額品を非常に低額や無償で譲り受けたりした場合なども贈与税の対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
(1)暦年課税とは?
暦年課税は、従来の方式の課税方法で、特に手続きをしなければ、この方法で贈与税が課税されます。贈与税には、年間110万円の基礎控除があり、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかからず、この場合は贈与税の申告が不要です。また、年間110万円を超える財産をもらった場合には、以下の式で贈与税を計算し、翌年の2月1日から3月15日までの間に申告が必要となります。
<贈与税の速算表>
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | - |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超 | 50% | 225万円 |
(例)贈与財産の価額の合計が400万円の場合
贈与税額=(400万円-110万円)×15%-10万円=33.5万円
(2)相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度は、平成15年に創設された贈与税と相続税を一体化した納税制度で、子供が親から受け取った贈与を、相続時に他の相続財産と一体化して課税するもので、贈与時には合計2,500万円の大きな特別控除枠があります。本制度は、一定条件を満たす親子間の贈与において、届出(手続き)をした場合に利用できます。
<相続時精算課税制度の概要>
| 対象者 | 贈与者=65歳以上の父母(住宅資金贈与の場合は年齢制限なし) 受贈者=20歳以上の子や代襲相続人である孫 |
|---|---|
| 対象財産 | 贈与財産の種類や金額、贈与回数に制限はない |
| 手続き | 受贈者が最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍謄本などの書類とともに「贈与税の申告書」に添付して提出する。なお、届け出は、贈与者(父または母)ごとに提出が必要となる。 |
| 贈与税の計算 | ・適用を受ける贈与財産は、選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、その贈与者(親)から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算する。 ・贈与税額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたって利用できる特別控除額※を差し引いた後の金額に、一律20%の税率をかけて求める。なお、特別控除額を差し引いた後の金額が0円の場合は、その年の贈与税額は発生しない。 ※特別控除額は最大2,500万円。前年以前に、この特別控除額を既に控除している場合は、残額がその年の限度額になる。 |
| 相続税の計算 | ・相続時精算課税制度による贈与財産(贈与時の申告価額)を相続財産に加算して相続税額を計算し、その税額から支払った贈与税額を差し引いて納付税額を計算する。 ・相続税額から控除しきれない贈与税額がある場合は、相続税の申告をすることにより還付を受けることができる。 |
相続時精算課税制度では、支払った贈与税は相続時に相続税として精算されるので、その家庭の税負担は、相続税相当額が限度となります。日本では遺産相続にあたって相続税がかかるのは5%程度ですから、相続税のかからない多くのご家庭(親子間)では、実質、非課税で贈与を実行できることになります。
一方で、相続税が発生するご家庭にとっては、相続時の精算によって税負担はプラスマイナスゼロになりますが、相続税計算の際には、贈与財産は贈与時の申告価額で加算されるため、値上がりが見込まれる不動産や株などをあらかじめ贈与しておけば、相続税が節税できる可能性があります。
なお、いったん相続時精算課税制度を選択すると、相続が発生するまで(親の死亡時まで)、この制度が適用されることになり、対象親子間では暦年課税の方法に戻すことはできないので、注意が必要です。
家族間の贈与の具体例について
次に、家族間で行われることの多い、生活資金や住宅資金の贈与、財産移転のための贈与について、具体的に見ていきましょう。
生活資金の贈与の場合
家族間での生活費や教育費の贈与、年末年始の贈答、弔事の際の香典など、常識的な範囲の金額であれば、贈与税がかからない財産とされています。ただし、生活費や教育費という名目で贈与されたものであっても、例えばそれを子どもが自分名義の預貯金にしたり、株式や不動産を購入する費用に充てたりした場合は、「通常必要な生活費」とは認められず、贈与税が課税されることになるので注意が必要です。
住宅資金の贈与の場合
住宅資金を贈与する際には、特例も活用して贈与税負担を抑える方法を考えましょう。
【親から子への贈与】
親から子へ相続時精算課税制度を利用して贈与する場合には、住宅取得の場合の特例があります(平成19年12月31日までの期間限定でしたが、平成20年度税制改正でさらに2年間延長予定)。この特例では、贈与者の年齢に制限がないので若い親子も利用でき、「住宅資金特別控除額」として1,000万円が上乗せされて特別控除額が合計3,500万円になります。
【配偶者間での贈与】
結婚してから20年以上たった夫婦の場合、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという制度があります。婚姻期間が20年を過ぎてからの贈与であること、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与の対象となった土地家屋に贈与を受けた妻(夫)が実際に住んでおり、その後も住み続ける見込みであること、などの条件を満たすことが必要です。なお、この控除は同じ配偶者間では、一生に一度しか使えません。
<住宅資金を家族間で出し合う場合の注意例>
| 住宅購入の際に資金を家族で出し合った場合、資金の負担割合に応じて所有権の登記をしないと、贈与税が発生する場合があります。例えば、総額3,000万円の住宅を購入し、夫が2,000万円、妻が1,000万円の資金負担をしたものの、所有権の登記は夫のみとしたとします。この場合、実際に夫が負担していない1,000万円分については、妻から夫への贈与とみなされるので注意が必要です。 |
| 子供の住む住宅に親の所有権が入っている場合、親が亡くなって相続が発生した際に、ほかの兄弟との遺産分割で問題になることがあります。これに対しては、あらかじめ兄弟にも相談するなどして、相続時にもめないように手段を講じておくことも必要です。 |
財産移転のための贈与の場合
将来の相続を考えて、贈与を行うことはよくあることです。生前贈与をしておけば、財産を確実に「あげたい人」に渡すことができ、将来、家族が遺産の分割でもめることを防ぐ効果も期待できます。親の財産を子どもに譲っておけば、親の相続財産を減らし、相続税の負担を減らすことになります。ただし、贈与のしかたによっては、思ったとおりの効果が得られない場合もありますので、例えば以下のような点にも気をつけましょう。
きちんと渡してこその「贈与」
きちんと生前に贈与できていなければ、贈与したはずの財産にも相続税がかかってくることがあります。例えば、子供の口座にお金を振り込んで贈与したとしても、その子名義の通帳や印鑑を親が管理していたら、贈与は成立していないとみなされてしまいます。
現金や預金を贈与する場合には、預金口座へ振り込んで贈与の事実を残し、通帳や印鑑はもらう側が管理する、また不動産や有価証券などを贈与する場合には、きちんと名義変更をしておくなど、贈与の事実を証明できるようにしておくことが必要です。
きちんと渡してこその「贈与」
年間110万円の基礎控除の範囲内で複数年に渡って贈与すれば、多額のお金を非課税で贈与することができます。しかし、毎年同じ金額を何年も贈与していくと(連年贈与という)、一括して贈与税がかかる場合があります。例えば、毎年110万円ずつ10年間贈与を行ったら、もともと1,100万円を贈与する意思があって、それを分割して贈与したものとみなされるのです。
したがって、毎年贈与する場合には、毎年贈与額を変える、年によっては基礎控除額を上回る贈与をして贈与税を支払う、毎年同じ時期に贈与しないようにする、などの工夫が必要です。また、毎年贈与契約書を交わして、その都度贈与の意思決定があったことを証明できるようにするのも有効でしょう。
以上、今回は、家族間の贈与で基本となる仕組みや注意点を取り上げましたが、贈与の活用法や節税の工夫は多種多様にあります。実際に贈与を実行される場合には、思わぬ税負担で後になって慌てぬよう、十分に情報収集したり、事前に税務署や専門家へ相談されたりするとよいでしょう。
大林香世(CFP®)